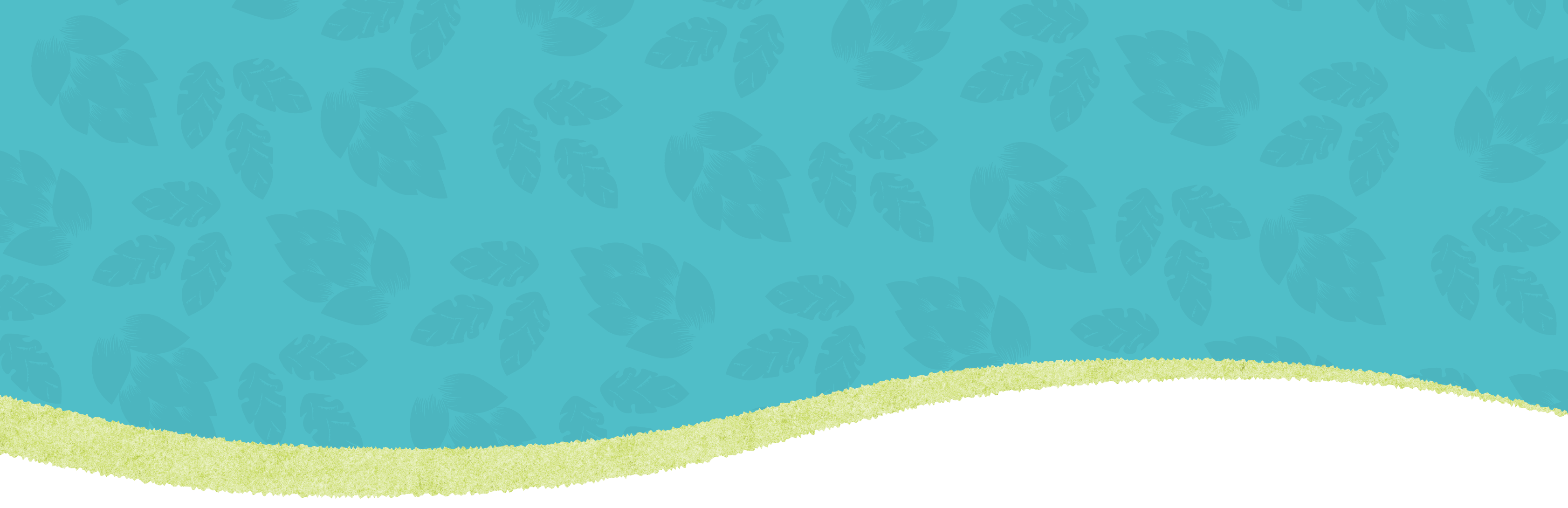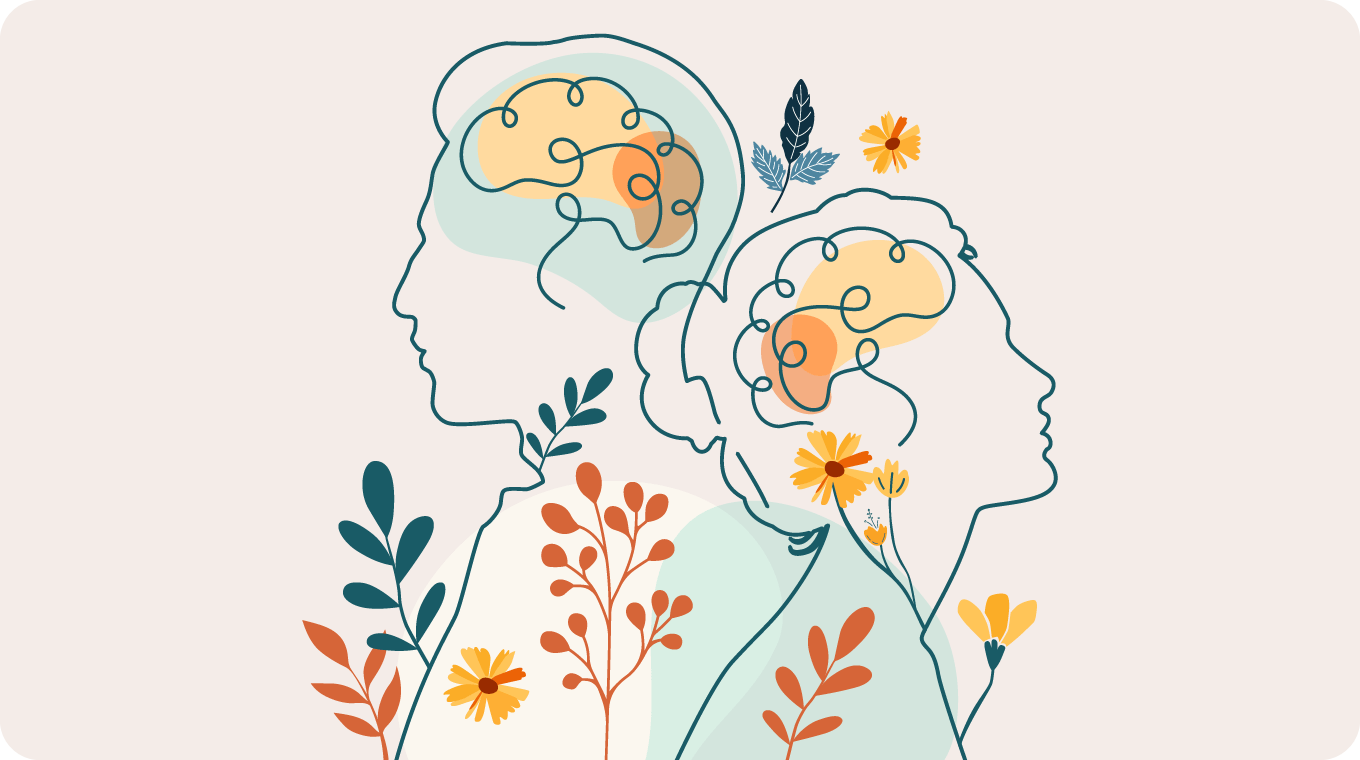ホップってハーブなの?

[ホップは伝統的なハーブ]
ハーブとは、香りや薬効などを通じて、心身の健康づくりに役立つ成分を含む植物のことを指します。単にお腹を満たすための作物というよりは、古くから香りづけや民間薬として利用されてきた植物と考えると、よりイメージしやすいかもしれません。
ホップもそのひとつで、古代から北半球各地でハーブとして用いられてきました。最もよく知られる機能は、睡眠を促す作用です。
インドの伝統医学「アーユルヴェーダ」では、ホップは睡眠促進に加えて、神経の緊張や頭痛をやわらげ、抗菌効果をもたらす薬草とされています1)。北米では、様々なインディアン部族がホップを様々な病気の治療薬として使用してきました2)。さらに歴史をさかのぼると、古代エジプトでホップが薬草として用いられていたことが報告されています3)。また、11世紀のアラビア語圏でもホップの薬効について言及した書物が出版されており、地域を問わず古くから人々の生活とともにあったことがうかがえます2)。
ところがヨーロッパでは、8世紀頃に薬として使われた形跡はあるものの、ハーブの中ではマイナーな存在でしかなかったのです。そんなホップにスポットライトが当たったのは1516年4月23日、ドイツでの出来事でした。そうです。「ビールは麦芽とホップと水だけで造るべし」と、バイエルン公国のヴィルヘルム4世が「ビール純粋令」を制定した日です。
14世紀以降ビールの風味づけには、さまざまな種類のハーブが組み合わされて使われてきたのですが、ホップにはビールの保存期間を延ばす優れた抗菌作用があることが明らかになり、文字通り一夜にして、ホップはビールの主役に踊り出ることになりました。ヨーロッパではこれ以降に、何人もの学者がホップの薬効について述べていますが、薬草としてのホップの利用がヨーロッパで盛んになるのは、なぜかずっと後のことだったのです。ホップはビール用というイメージが強くなり過ぎ たからなのかもしれませんね。
参考文献
1) Int J Pharmacogn Phytochem Res. 2021;22(3):558–572.
2) Biendl M, Pinzl C. Hops and Health: Uses, Effects, History. German Hop Museum; 2013.
3) Life (Basel) 2022 Nov 29;12(12):1993.